発掘調査を始める前に調査地周辺の空中写真を撮りました。ラジコンヘリコプターにカメラを積んで空から遺跡を撮影します。
潟湖である湖山池に近い扇状地にあるという遺跡の立地がよくわかります。

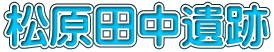
発掘調査を始める前に調査地周辺の空中写真を撮りました。ラジコンヘリコプターにカメラを積んで空から遺跡を撮影します。
潟湖である湖山池に近い扇状地にあるという遺跡の立地がよくわかります。
発掘調査に先立って地表下5mまでの地層の状況を確認するため、ボーリング調査を行いました。
直径約10㎝の円柱状の土や砂のサンプルを採取して、どのような土砂が堆積しているのか、またその中に遺跡が存在しそうな層はありそうか等を調べます。
現代の地層を取り除いたところ、調査区全域で平行するいくつもの溝が見つかりました。
江戸時代以降の田畠の跡と思われます。
耕作土中から銅鐸の小さな破片が出土しました。
銅鐸とは釣鐘形をした弥生時代のマツリの道具ですが、出土したのはその裾に近い部分の破片です。
銅鐸の「内面凸帯」と呼ばれる部位の破片です。この部位は銅鐸の内側に吊した「舌(ぜつ)」と呼ばれる棒が当たって音を鳴らす、銅鐸にとって大切な部分です。
調査地の北東部と南部で、掘立柱建物が各1棟見つかりました。
どちらの建物も、柱穴の中や周辺から見つかった土器から推測すると、古墳時代後期後半(約1,450年前)以降の建物になりそうです。
2棟とも建物の外周に柱がめぐる側柱(がわばしら)建物と呼ばれるもので、建物の向きは西北西-東南東です。
北東部の掘立柱建物1〔写真上〕は桁行(けたゆき、長軸方向のこと)2間以上(4.2メートル以上)・梁行(はりゆき、短軸方向のこと)2間(約3.5メートル)で、東側は調査区の外へと続くようです。
一方、南部の掘立柱建物2〔写真下〕は桁行3間(約6.1メートル)・梁行1間(約2.8メートル)の細長い建物で、東面に庇(ひさし)をもち、規模や構造が異なっています。
古墳時代後期後半(約1,450年前)から中世(約600年前)にかけての建物や溝、ピット(穴)が見つかった第4面の調査を終え、高所作業車から全景写真を撮影しました。
心配していた天気も、見事に快晴!となり、一安心です。
第4面の下ではどんな発見があるのか…、今後の調査が楽しみです。
現在、古墳時代のムラの跡を調査中で、溝や多数の柱穴が見つかっています。
このうち、調査区北側で見つかった古墳時代前期(約1,700年前)の溝の中から壺や、煮炊きに使う甕(かめ)、壺などをのせる器台(きだい)といった土器がたくさん出土しました〔写真上〕。
溝の中の土器は粉々に割れていて、石や木片とともに炭交じりの土から出土しています〔写真下〕。
この溝の底は北側へ下がるように傾斜しているため、元は排水路の役割を果たしていたと考えられますが、ムラの祭りで使った土器などを投げ捨てて埋められたようです。
古墳時代後期(約1,400年前)の溝の中から、他の土器に混ざって珍しい文様をもつ弥生土器が出土しました。
この弥生土器は器台(きだい)の上半部(※上下が反対になって出土しています)で、3重の同心円文のスタンプ文様を1列に並ぶように入れています。
同心円や渦巻き文様のスタンプを押して飾る土器は、弥生時代後期(約1,800年前)に山陰地方を中心として見られるようになり、ムラの祭りに使われた土器ではないかと考えられています。
(※図は写真の土器と同じ頃の器台で、鳥取市秋里(あきさと)遺跡で出土したものです。)
調査区西端で、南西-北東方向に直線的に伸びる古墳時代前期(約1,700年前)の溝が見つかりました。
この溝の中だけでなく西側(写真右側)にもたくさんの土器や石が捨てられていて、足の踏み場もない状態でした。
この溝より西側の松原田中遺跡3区・4区は弥生時代~古墳時代前期頃の柱穴などが多数見つかっていて、ムラの中心部に近い場所と推測しています。
ところが、溝の東側(写真の左側)ではその時期の遺構・遺物ともほとんど見られません。
もしかすると、この溝はムラの中心部の東境に掘られたものかもしれません。
古墳時代後期(約1,500年前)の掘立柱建物が3棟見つかりました。
建物6(緑色)は東西4.6メートル、南北5.6メートルで、3つの建物の中では一番新しく、いくつかの柱穴には直径20センチほどの柱が残っていました。
建物5(黄色)は東西4.0メートル、南北5.4メートルで、建物6と規模や柱穴配置がほぼ同じことから、建物5→6の順に建て替えられてのかもしれません。
建物4(ピンク色)は東西 3.9メートル、南北3.2メートルで、建物5・6と比べ一回り小さい建物です。
いずれの建物もその大きさから考えて、倉庫ではないかと推測しています。