野坂川右岸の丘陵には、たくさんの古墳が造営されています。
鳥取西道路の建設に関連して、鳥取市嶋にある宮谷古墳群で発掘調査をすることになりました。
調査を行うのは、野坂川に面した丘陵斜面に造られた円墳、宮谷26号墳です。
まだ、墳丘の規模や、築造された時期など不明な点が多い古墳です。
発掘調査でいろいろなことを明らかにできればと思います。


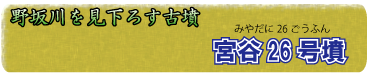
野坂川右岸の丘陵には、たくさんの古墳が造営されています。
鳥取西道路の建設に関連して、鳥取市嶋にある宮谷古墳群で発掘調査をすることになりました。
調査を行うのは、野坂川に面した丘陵斜面に造られた円墳、宮谷26号墳です。
まだ、墳丘の規模や、築造された時期など不明な点が多い古墳です。
発掘調査でいろいろなことを明らかにできればと思います。
今日は、カメラを搭載したラジコンヘリコプターで、宮谷26号墳を上空から撮影しました。
調査前の遺跡が、どのような状態にあったかを記録することも発掘調査の重要な仕事の一つです。
古墳の現況を記録するための測量も終わり、これから本格的に発掘を始めるための準備作業にとりかかりました。
これから、古墳の上に堆積している表土を剥ぎながら、古墳の形を確認していく予定です。
表土剥ぎも終わり、お盆明けから、古墳の上に堆積した土を取り除く作業を行っています。
足場の悪い斜面での作業に悪戦苦闘中ですが、少しずつ古墳の形が見えてきました。
古墳の形も明らかになってきたので、古墳周辺の作業に併行して、墳頂部の調査も行うことになりました。
これから埋葬施設の検出に取りかかります。
墳頂部で須恵器の破片が見つかりました。
どうやら、甕の破片のようです。
埋葬施設の上部に、供えられたものかもしれません!
これから、周辺の土も取り除きながら、須恵器片の広がりを確認していきます。
埋葬施設の上部に盛られた土を取り除くと、墓穴の形が見えてきました。
墳丘の盛土と、埋葬施設の埋土が、とてもよく似ており、大きさと形を見極めるのに苦戦しましたが、どうやら2つの埋葬施設が重なり合っていることがわかりました。
最初に埋葬された墓穴を「墓坑1」、墓坑1の上に造られた墓穴を「墓坑2」と名づけ、調査を進めることにしました。
墓坑2の規模は、長さ180㎝、幅70センチほど。
掘り始めると、移植ゴテの先にコツンという手ごたえが!たくさんの須恵器(すえき)がお供えしてあることがわかりました。
墓坑2からは、墓穴の北側を中心に、提瓶(さげべ)という水筒のような器と、たくさんの高杯が出土しました。
墓穴の底から浮いた状態のものがあることから、箱式木棺の上部に置かれていた須恵器が、棺の蓋が腐食した際、棺内に落ち込んでしまったのではないかと思われます。
墓坑2の調査に引き続き、墓坑1の調査を行いました。
ここでも、掘り始めると、移植ゴテの先にコツンという手ごたえが!!!
須恵器の壺と土師器(はじき)の破片が姿を現わしました。
土師器の破片は壺の蓋に使用されていたのではないかと思われます。
墓坑1は長さが3mほどある長大な埋葬施設です。この大きなお墓には、いったい、どのようなものが副葬されているのか?楽しみです。
壺の周囲の土を慎重に取り除くと、須恵器の杯や高杯が姿を現わしました。
他にも、鉄の鏃(やじり)など、小型の鉄器が出土しました。
墓坑1が掘り上がりました。
須恵器は墓穴の南側に置かれていました。
残念ながら・・・、須恵器と、小型の鉄器以外には、副葬品は見つかりませんでした。
墓坑1・2ともに、出土した須恵器(すえき)から、6世紀末~7世紀初めごろに造営された古墳であると考えられます。