本高弓ノ木遺跡では、古墳時代前期の水路の中に造られた木製構造物の調査を再開しました。
木材は、1600年以上の時を経たとは思えないほどよく残っていて、造られた当時のようすを伝えてくれます。
今後は、これらの木材を解体しながら取り上げ、構造物の構築方法や順序を調べていく予定です。


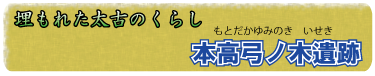
本高弓ノ木遺跡では、古墳時代前期の水路の中に造られた木製構造物の調査を再開しました。
木材は、1600年以上の時を経たとは思えないほどよく残っていて、造られた当時のようすを伝えてくれます。
今後は、これらの木材を解体しながら取り上げ、構造物の構築方法や順序を調べていく予定です。
本高弓ノ木遺跡の南側では、古墳時代前期に造られた木製構造物の調査が続いています。
その作業の中で、木製構造物の間に積まれた「土のう」がみつかりました。
一つ一つの土のうの「幅」は、約40センチ、「長さ」は、はっきりとわかりませんが、60~70センチ以上あります。
表面にはワラのような植物の茎がそのまま残っており、ひとつひとつの土のうの大きさや形まで観察できます。
地中で腐って痕跡をとどめない土のうの発掘調査例は、非常に少なく、表面の植物質まで残る例としては、国内最古のものとなると考えられます。
復元イラストで示すと、このような感じでしょうか。
土を詰めた重い土のうを積み上げるのは、重労働だったでしょう。
さらに驚くべき発見がありました。
土のうの表面を丁寧に調査していくと、土のうを横に横切る白い筋を発見しました。
土のうを横に縛る「ヒモ」の痕跡です。(ヒモの幅は約1センチ)
しかも、その中央には結び目が!
土圧によって押しつぶされているものの、結び方まではっきりわかります。
ヒモや縄は、長い年月の間に腐ってしまうため、古代におけるヒモや縄の材質や結び方については、意外とわかっていません。
水気の多い地中で、約1600年もの間、保存されてきた土のうは、当時の土木工事のようすを伝えるだけではなく、モノを結ぶ方法や技術の謎をヒモ解くカギとなるかもしれません。
木製構造物の間で、板を敷き並べたようすがみつかりました。
板には小さな四角い穴があいているものがあり、建物の壁板などを転用している可能性があります。
また、板の上から、細い角材を台形に組み合わせた構造物がみつかっています。
もともとは建物などの建築部材の可能性があります。
今後はこれらの材を取り上げたのちに、細かく調べていく予定です。
木製構造物は、水が運ぶ土砂などで埋もれるたびに、修復や増築がなされています。
写真1は、池の中に木製構造物が造られはじめたころの段階の状況。
少し方向の違う構造物が、重なり合っているようすがわかります。
写真2は、池から伸びる水路の取水口付近。
大きな石を積み上げて堤防のようなものをつくっています。
水が通る場所へ石が落ちないように、木で支えているようすも確認できました。
高草中学校の職場体験「ワクワクたかくさ」が実施され、その一環で、本高弓ノ木遺跡での発掘調査を体験してもらいました。
古代の木製品などを掘り出すのに戸惑った様子でしたが、ベテラン作業員の方に指導をしてもらい、熱心に作業を進めていました。
梅雨の晴れ間の暑い日。
汗をかきながら行う作業はつらかったと思いますが、自分の手で、はるか昔の木製品や石積みなどを掘り出していく、遺跡発掘のおもしろさも味わってもらえたのではないでしょうか。
雨上がりの月曜日、発掘現場に着いてビックリ!
1600年前を彷彿とさせる景観が突如として現われていたのです!
夜間に降った大雨で、排水ポンプが止まってしまい、古墳時代の池は、満々と水を湛えていました。
調査を進めてきた木製構造物は水没。
排水が完了するまで発掘調査が再開できません。
まぁ、当時の姿を考えるいい機会になったと思うことにしましょう・・・
解体中の木製構造物の間から、小さな土器が見つかりました。
調査補助員で活躍中のOくんは、
「お酒とかを呑む、おちょこですか?」と一言。
いえいえ違います。おちょこではありません。
だって、そんなに小さかったらほとんど入りませんよね?
弥生時代から古墳時代ごろの遺跡では、日常的に使う土器をかたどった「ミニチュア土器」がときどき見つかります。
何に使われたのかははっきりわかっていませんが、祭祀や「まじない」に使われたのではないかと考えられています。
古墳時代前期(約1600年前)の水路をついに掘りきりました。幅5m、深さ1mほどの規模で、調査地内だけで約200m続いており、さらに北側へとのびています。
これほど大規模な水路ですから、単なる水田の導水路としてだけでなく、船で行き来が出来る運河としての役割があったかもしれません。
5月から再開した木製構造物の調査もいよいよクライマックス。
おそらく一番古い時期に造られた木製構造物の調査に着手しています。
太い横木やしっかりした杭、背面には構造物を支える「支保材」も確認できます。
人の背丈ほどの高さで構築された木製構造物、まだまだ一筋縄ではいきそうにありません・・・
調査地北東隅で、土を盛ってつくった台状の遺構が見つかりました。またその盛土の周囲には、幅5~6mの溝が巡っています。盛土の範囲は20×18mほどの長方形なのですが、その四隅の角のうち、2つの角は細く突き出ており…。
この盛土遺構の性格を知るために、今後も慎重に調査を進めていきます。
古墳時代の池の中に設置された、木製構造物の解体調査がついに完了しました!
池の底は水の流れによってえぐられ、でこぼこしています。
激しい水流を制御して利用するために、木製構造物が造られたことがわかります。
発掘調査を完了したあとの池。
24時間稼働していた「排水ポンプ」を止めたところ、みるみるうちに水を湛えはじめました。
調査中も、このわき水には苦労させられたものです・・・
ひと泳ぎできるくらいの深さがありますが、危ないので近寄らないようにしてくださいね。
本高弓ノ木遺跡調査地の北側では「4区」の発掘が始まりました。
4区は、4ヶ所の調査地に分かれており、北の方から順番に4-1区~4-4区と呼んでいます。
鋼矢板に囲まれた調査区の中に、ショベルカーの爪が入り、いよいよ掘削の開始です。
ここではどんな発見があるのでしょうか。
期待が高まります。
ショベルカーによる掘削も終わり、今度は発掘作業員さんの手によって遺跡の土が掘り下げられていきます。
まず見えてきたのは、平行する何本もの浅い溝。
上部が削られていてあまりはっきりとはわかりませんが、畑の畝(うね)の間につくる溝の可能性があります。
地層の観察から、古代から中世のものと考えられますが、遺物の出土がないため、はっきりとはわかりません。
5区の北側で、弥生時代後期(約2000年前)の水路がみつかりました。
(写真は西側から撮ったもの)
以前お知らせした古墳時代前期の水路が、南北方向に真っ直ぐ伸びているのに対して、この水路は東西方向に伸び、釣山の山裾で大きく曲がり、北方向に流れを変えています。
土砂で埋まった後に、掘り直した跡もみつかっており、当時の人々の生活にとって、大切な水路であったと考えられます。
田んぼの耕作土と考えられる土を掘り下げていくと、牛の足跡がたくさんみつかりました。
直線的に並ぶ足跡からは、歩いた方向が推定でき、田んぼの中を何度も往復しているようすがわかります。
田植え前に田んぼに水を入れて、土を混ぜてやわらかくすることを「代かき」といいます。
現代ではトラクターなどの農機具を使いますが、昔は牛や馬などの家畜を使って行っていました。
この田んぼの耕作土からは、飛鳥時代(1400年ほど前)の土器がみつかっていますので、その頃の足跡かもしれません。
5区の北側でみつかった弥生時代後期(約1900年前)の溝を掘り下げていくと、土器の破片や木製品など様々な遺物が出てきました。
その中にかわった形をしたものが。ゆるく曲がった棒の先に丸い頭、さらにその先端が細く突出しています。
これは「斧の柄」です。頭の先の細い部分に、鉄製の斧を差し込んで使います。
突出部分の幅は2cmほどで、木を切り倒すには小さすぎます。おそらく木の加工などに使う小さい斧だったのでしょう。
4-4区で、地層を観察するために掘り下げを行ったところ、断面に大きな溝がみつかりました。
まだ調査をしていないので、詳しいことはまだわかりませんが、幅は2m以上(東側は調査区外に広がります)あり、底が見えないくらい深いものです。
西側にも同じような大きな溝があり、矢板の中の小さな調査区とはいえ、今後の調査への期待が高まります。
弥生時代後期(約1900年前)の溝と盛土遺構の写真を撮影しました。
今回はラジコンヘリを使っての航空撮影。溝や盛土遺構は広範囲にあるため、高い場所からでないと全体をとらえられません。
今にも雨が降り出しそうな天気でしたが、撮影は無事終了。前日につくったてるてる坊主のおかげでしょうか…?
現場近くの田んぼにたたずむ黒い影。
なんだろうと見ていると、突然走り出しました。
工事用道路を横切って、山に逃げ込んだのは立派な角を持ったオスの鹿。
思わぬ珍客に、みんな発掘の手を止めて見入ってしまいました。
遺跡のやわらかい泥の上に、人や牛の足跡がみつかりました。
みつかった地層の年代から、古墳時代の中頃から終わり頃(約1400~1600年前)にかけてつけられた足跡だと考えられます。
足跡は砂できれいに覆われていたので、石こうで足形を採ってみることにしました。
①砂で埋まった足跡がみつかったところ
②砂を丁寧に取り除くと、足跡のくぼみがはっきりします。
③足跡のくぼみに、水で溶いた石こうを流し込みます。
④石こうが乾いたころ、取り外すときれいに足形が採れました。左のものが人の足跡、右の2つは牛のひづめの跡です。
これらの足形は、11月3日に開催する現地説明会で展示する予定です。あなたの足と比べてみませんか?
釣山の裾をはしる溝の斜面で、鹿の足跡がみつかりました。
V字に開いたひづめの跡がいくつか、斜面を駆け上ったようについています。
釣山から下りてきた鹿がこの溝を越えて行ったのでしょう。
弥生時代には滑りやすい溝、現代では車の走る道路。
いまも昔も、山から山へ移動するには障害物がつきもののようです。
盛土遺構を囲む溝の底で、溝を掘った工具の痕がみつかりました。
クワやスキで掘ったくぼみに別の土が溜まったもので、その土をとると、幅約15㎝、深さ2㎝ほどになりました。ここから、使用した工具の刃先の大きさが分かります。
また、この工具痕は列状に並んでおり、人が実際に動いて溝を掘っていった様子も知ることができます。
10月6日の記事でお知らせした大きな溝が掘りあがりました。
溝は2本みつかっています。
写真左側の溝は、遺跡の南方からずっと続いている古墳時代前期の水路と考えられ、その延長距離はみつかっている範囲だけで200m以上におよびます。
周辺の開発にかかわる重要な水路だったのでしょう。
また、溝の中からは、板材や棒材などの木製品がみつかっています。
これらには組み合わせたり、溝に打ち込まれたようすはなく、溝内のあちこちに散らばった状態で出土しています。
流れてきた木材がそのまま埋まってしまったのでしょうか。
4-4区でみつかった大きな溝の底を掘り下げていくと、木製品や土器がみつかりました。
①は、円い板が半分に割れたような木製品。
中央に切れ込みがあり、なにかと組み合う部材になるかもしれません。
事務所に持ち帰った後、泥を洗い落として、詳しく調べていきますが、それまでに乾燥しないよう、ビニールのラップにくるんでおきます。
②は、丸い底の壺。
形の特徴から、古墳時代前期頃(1600~1700年前)のものと考えられます。
口が一部欠けていますが、ほぼ完全な形でみつかりました。欠けた口の破片は、探してみたのですがみつかりません。
去年の調査でも同じ時期の溝から、口の部分が欠けた土器がいくつかみつかっており、壊れていない土器の一部をわざと壊して、溝に入れた(埋めた)と考えられます。
そこには、古代人のどのような思いが込められているのでしょうか・・・
4-3区で、縄文時代の地層を掘り下げている途中で丸い石がみつかりました。
石の中央には、わずかなくぼみがあり、裏面にも同じくぼみがあります。
これは凹み石(くぼみいし)と呼ばれる石器で、縄文時代の遺跡からよくみつかります。
その用途については、まだはっきりとわかっていません。
ドングリなどのかたい実をくぼみに据えて、たたき割るためのものだとか、矢じりなどの石器を作るときに固定するためのものだとか、諸説があります。
凹み石がみつかった地点のすぐそばでは、大きな石もみつかっています。
石の表面にはっきりと人為的な痕跡がみえるわけではありませんが、平らな面がちょうど水平になるように出土しており、なにかの作業をするときの台として使ったものかもしれません。
5区の北側には東から西に流れる大きな溝があります。その溝を埋めている砂の中から、土器の破片が大量にみつかりました。
そのほとんどが縄文時代の終わりごろ(約2500年前)に使われていた土器ですが、その中に縄文土器とは違う土器が混ざっていました。
形状から、この土器はもっとも古い弥生土器であることがわかりました。同じ時期の土器は、これまで鳥取県の中・西部ではみつかっていましたが、東部でみつかった例は初めてです。
鳥取平野でも、縄文時代が終わる頃に、お米づくりに象徴される弥生文化が少しずつ浸透してきたようすを知る上で、非常に重要な発見です。
4-4区で、調査区の隅から大きな木がみつかりました。
片側は残念ながら調査区外に続くため、全体の形は確認できませんが、縦半分になった丸木の内側がくりぬかれ、先端が細くなるように加工されていることから、丸木舟だと考えられます。
舟の近くからは、土器がみつからなかったため、いつの時代のものかははっきりしませんが、弥生時代中期(約2000年前)に埋まった溝の下の地層から出土しているため、それ以前のものと考えられます。
はるかな昔、本高に住む人々は、カヌーのような形をしたこの舟で、海や川にこぎ出していったのでしょうか。
5区北側の弥生時代前期の溝からは大量の木が出土しています。
ほとんどが丸太で、なかには長さ約11m、太いところで直径1mの木もあります。
枝が付いておらず、樹皮がはがされていて、斧で削った跡もついていることから、倒れた木が流れ込んできたのではなく、人が切り出した木を溝の中に貯めていると考えています。
道具に加工するために木を割った状態で貯めている例は多くありますが、丸太だけというのは、全国的にもめずらしい例です。
100本を超える大量の木は、何に使うために集められたのでしょう。
みつかった丸木舟は、乾燥すると割れたりして傷んでしまうため、写真や図で記録をとった後、すぐに取り上げ作業を行いました。
長い年月の間に水を含んだ木材は、とても重く人の手では地上まで持ち上げられません。
しっかりと保護養生をして、ショベルカーのフックで吊り上げることにしました。
触れるだけで壊れてしまいそうな丸木舟を、ゆっくりと数センチずつ吊り上げていきます。
作業の間はとても緊張しましたが、なんとか無事に吊り上げることができました。
工事用の矢板に切られていた舟の断面を見てみると、底が5~6センチくらいと厚いのに対し、側面は2センチくらいと薄くなっています。
船底は厚く丈夫に、舟の側面は軽くなるように薄く削っているのでしょう。
弥生時代前期(約2500年前)の溝を掘り下げていると、器が出てきました。ただし、土器ではなく木の器です。
半分に割れていましたが、お椀のように丸みをおびており、底の部分には下駄の脚のようなものが付いています。
どうやら「二脚盤」と呼ばれる二本の脚が付いた容器のようです。
この容器は以前お伝えした丸太よりも下の層から出土しています。丸太を貯める前にはこの溝をどのように利用していたのでしょう。これから出てくるものと合わせて考えていきます。
弥生時代前期の溝に貯められた木は、形や出土した状況などを記録した後、木の種類を調べるために、一部分を切って持ち帰っています。
しかし、それらの木の中でもひときわ目立つ大きなケヤキは、かたすぎてチェーンソーの使用に慣れた発掘作業員さんでも切ることができません。
そこで、森林組合の方に来ていただき、切断してもらうことになりました。今度はあっという間に切れていくケヤキを見ているとプロの技を感じます。
それにしても、チェーンソーでもなかなか切れない木を石の斧で切るのには、どれだけ時間がかかったでしょうか。
弥生時代の人々が木製品をつくるのは、想像以上に大変なことだったのかもしれません。
弥生時代前期の溝を北へ掘り進めていくと、たくさんの丸太や石でつくられた構造物がみつかりました。
よくみていくと、石や木を組んで「せき」をつくっている部分や、何本かの丸太を「井」の字形に組んでいる部分、溝の斜面を石で護岸している部分などがあります。
弥生時代の本高の人々はこれらの施設で水の流れを調節し、木を貯めたり、水場での作業を行っていたのでしょう。
木を貯めたり、構造物をつくっていた弥生時代前期の溝が、ついに掘りあがりました。
これで2年にわたった本高弓ノ木遺跡の調査も終了です。
最後に溝の底から見上げると、現在の道路は頭のはるか上。ここまで調査をすすめてこれたのは、暑さや寒さの厳しい中でがんばっていただいた発掘作業員さんたちのおかげです。
今後は出土遺物の整理を進めながら、本高地域の歴史を明らかにしていきます。
本高弓ノ木遺跡で出土した木製品の中から鍬がみつかりました。
裏返しの状態で出土していましたが、ひっくり返すと突起があり、柄を差し込む穴もあいています。
真ん中近くでたてに割れているため、半分ほどの幅しか残っていませんでした。
今年度の調査では、松原田中遺跡で作りかけの鍬もみつかっています。松原田中遺跡のものも完成するとこのような鍬になるのかもしれません。